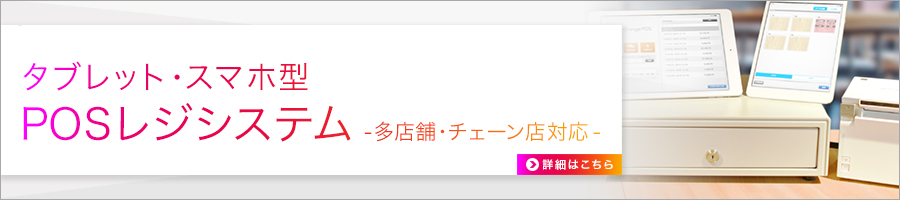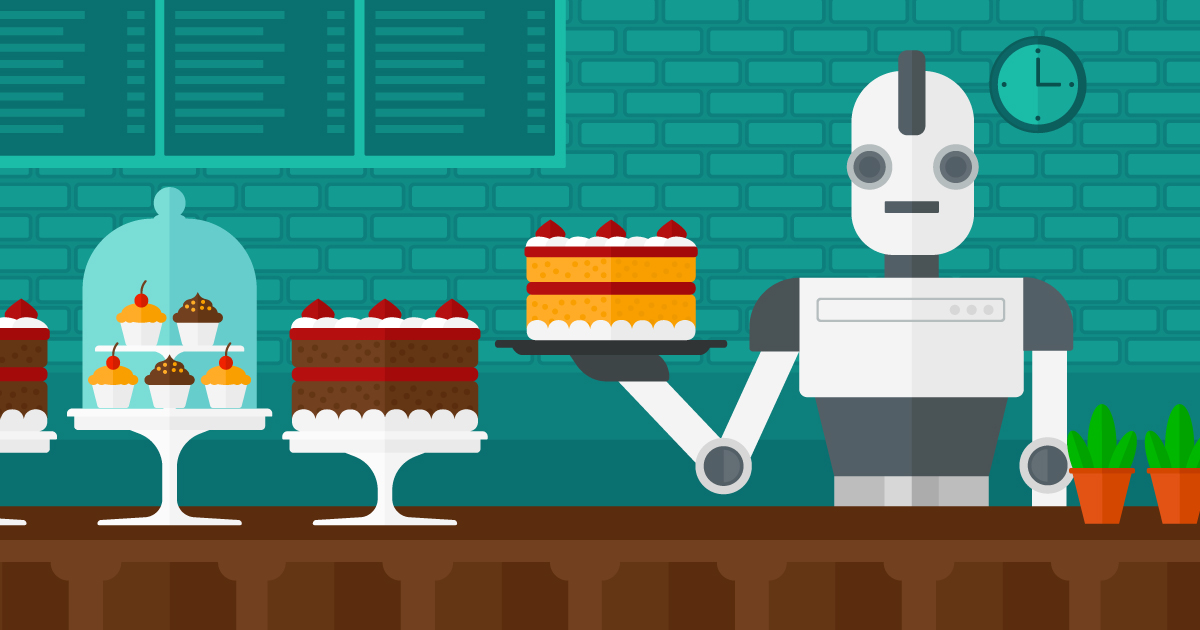インドのPOSアプリ「OKCredit」とは?進化する東南アジアの技術について

日本の店舗でもよく使われるPOSシステム。インドでは小規模の店舗向けに、スマートフォンアプリでPOSシステムを導入できる「OKCredit」がリリースされました。2017年設立のスタートアップ企業にも関わらず、18億円を超える資金集めに成功しています。
OKCreditが出資者を期待させた理由やインド特有のIT事情、インドに進出した日系企業についてご紹介します。
OKCreditとはインドの小規模小売店向けのPOSシステム
OKCreditはスマホで販売管理ができるアプリ
OKCreditは、POSシステムを導入していなくてもスマホでPOS管理ができるアプリです。アプリは無料でインストール可能で、購入データを電子化して分析することができます。アプリはAndroidのみ対応しており、iOS版はリリースしていません。
参照:Google Play「OKCredit」
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.okcredit.merchant&hl=ja
紙媒体の台帳で、購入や仕入れ情報を毎日記入するのは大変手間ですが、POSシステムを導入したくても、費用がネックで踏み切れない店舗もあるでしょう。
しかしOKCreditなら無料でスマートフォンにインストールできるため、スマートフォンを持っていれば費用がほとんど発生しません。POSシステム導入のコストを大幅に抑えることができます。

出典:https://okcredit.in/
ターゲットはインドの小規模小売店
OKCreditはインドの小規模小売店向けに開発されており、仕入れ業者も利用できる仕様になっています。
インドといえば「キラナ」と呼ばれる小規模小売店がメジャーであり、古くからインド人に受け入れられています。キラナは日本のコンビニのような位置づけで、インドの食品や日用品の市場で98%ものシェアを占めており、インド人の生活に欠かせません。
“パパママストア”とも称されるキラナはインドに1,200万以上あるといわれ、店舗密度が高いのも特徴。自宅の近くに設置して家族経営するのがキラナの一般モデルであり、インド人の生活を支えています。
参照:三井物産研究所「インドの⼩売流通で広がるキラナショップのビジネス活⽤」
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/10/09/1810x_nozaki.pdf
キラナはインドの貧困層にも浸透しており、その日使う分だけのシャンプーを4円で買うという文化もあるほど。そのため1店舗の売り上げも高いものではなく、POSシステムの導入は金銭的に厳しいのです。
OKCreditは、そんなインドの小規模小売店向けに開発されたPOS管理アプリ。最近ではキラナにもITやEコマースが登場しているため、多くのインド商店がOKCreditに価値を感じるでしょう。
OKCreditは2017年に結成されたスタートアップ企業
アプリを開発したOKCreditは、インド工科大学の卒業生3人で設立された会社です。2017年に設立したスタートアップ企業で、複数のファンドから資金を集めてアプリの提供を行っています。
OKCreditはインドの小規模店舗向けの無料アプリであり、有料化するとユーザーは減ってしまうでしょう。日本の無料アプリでも一部有料コンテンツを設ける方法はよくあるので、OKCreditでも今後は有料コンテンツを作ることで利益を作るかもしれません。
約18億の資金集めに成功
インドでもスタートアップ企業は資金調達を行いますが、OKCreditは調達金額が最大級であったことが話題になりました。
OKCreditは2回資金調達を行いましたが、合計すると1750万ドル、日本円にして18億円もの資金集めに成功しています。5億円でも“大型”と言われることを考えると、その桁違いの金額に驚かされます。
インドでも、AIやVRといった最新技術を用いたスタートアップ企業が多数存在。その中でも出資者たちは、OKCreditの可能性を大きく感じていることが伺えます。

インドや東南アジアのユニコーン企業には日本も投資している
SoftBankはAI技術を持つ海外企業に投資
実は日系企業も、インドをはじめ海外の企業に投資を行っています。2019年7月に行われたSoftBank World 2019では、初日の基調講演に孫正義氏が登壇。SoftBankが投資している海外の企業について紹介しました。
孫氏は基調講演で、「日本はAI後進国になってしまった」と嘆きます。AIをビジネス活用しきれておらず、海外のベンチャー企業に期待している旨を発表したのです。
■関連記事:AIは未来予測に活用すべき:SoftBank World 2019基調講演レポート
OKCreditで電子データを集められるようになれば、その次は“データの活用”という課題があります。データの分析や推論が得意なAIは、OKCreditにとっても必要な技術となるかもしれません。
東南アジアのAI技術は日本も利用している
同基調講演で孫氏が発表したスタートアップ企業を一部ご紹介します。
OYO(オヨ)
AI技術と行動力で世界2位を記録したOYOは、わずか25歳のCEOが動かすホテルチェーン企業。ヒルトン・ホテルズも抜くほどの勢いがあり、世界80か国110万もの客室を保有しています。
ホテル企業が使うAI技術といえば予約管理のイメージが強いですが、OYOはさらに広範囲でAIを活用。インテリアデザインにまでAIを活用することで、稼働率が3倍にアップ。さらに、客室清掃管理のアプリも導入することで、生産性が2.5倍も上昇しました。
勢いを増すOYOは、2023年までに東南アジアだけで200万室を超える客室の設置を計画に掲げています。
Paytm(ペイティーエム)
電子決済サービスを展開しているPaytmは、日本でキャッシュレスブームを作った「PayPay」が技術支援を受けたことでも知られています。
Paytmはインドを中心に電子決済サービスを展開しており、2014年には0.2億人ユーザーであったのが、2018年には4.08億人と2,000%も増加しました。
モバイル決済(Pay through Mobile)の頭文字を取って名付けられたPaytmは、スマートフォンアプリを介した電子決済が主力の企業。インドでは2016年に紙幣改革があり、日本と同じく脱現金化を実行。Paytmにとって追い風となり、今ではインド最大の電子決済システムとなっています。
OKCreditが資金集めに成功した理由
OKCreditが巨額の資金集めに成功した理由は、以下の3つが考えられます。
OKCreditはすでに130万ダウンロードを記録
スタートアップ企業が開発したスマホアプリが100万を超えるダウンロード数を記録したという点に、まず出資者たちは興味を持ちました。
アメリカのヘッジファンドとして有名なタイガー・グローバルなどもそのダウンロード数を高く評価して、OKCreditに出資しています。さらにOKCreditが期待されるのは、すでにアクティブユーザーが90万を突破しているという点。
今後インドの小規模小売店にとって、不可欠なアプリになる可能性があります。
POSシステム不要で紙管理から解放される
売上金や販売データを紙で管理すると、手間が多いほかに人為的ミスが発生します。帳簿の数が合わず数字を確認し直すのは、かなりの工数を割かなければいけません。
しかしOKCreditのように毎日の売り上げなどをデータで管理できれば、紙よりもずっと効率的になります。インドの小売店舗にとって、この工数削減は大きな魅力となるでしょう。
インド工科大学(IIT)は世界的にハイレベル
OKCreditを設立した3人は、インド工科大学出身です。インド工科大学は世界的に見ても教育レベルが高く、合格率はわずか1%という低さ。
インド工科大学の出身者にはGoogleの代表サンダー・ピチャイ氏、SoftBank副社長のニケシュ・アローラ氏などがおり、IT業界で活躍しています。
マサチューセッツ工科大学(MIT)よりも上と評されるインド工科大学の出身者は、IT企業もこぞって採用したがります。FacebookやGoogleは、インド工科大出身者に1,400万円もの年収を提示することもあり、争うように卒業生を確保しているのです。
参照:DIAMOND online「インド工科大がマサチューセッツ工科大を超えた理由」
https://diamond.jp/articles/-/91668

インドが技術先進国になった背景
IT技術が「カースト制度」に苦しむインド人を救う
インドといえばIT技術に長けており、優秀なエンジニアが多く活躍しています。そのようにIT技術者が増えた背景には、インド独自の宗教が深く関わっているのです。
インド古来のヒンズー教には、過去にカースト制度がありました。カースト制度は田舎にいくほど色濃く残っており、職業や結婚相手に対する厳しい規制が残っています。低い身分出身の人は、優秀であっても職業の制限により貧困から抜け出せない状況が続いていました。
しかしITは先進技術であり、ヒンズー教の教えに縛られることがありません。低い身分に苦しんでいたインド人にとって、IT技術は貧困脱出の数少ない手段となります。
そのため、インド工科大学への高い合格率を誇る塾は、貧しい地域出身の生徒が多くいます。日本と違いシビアな環境を生き抜いているため情熱を燃やすエンジニアが多く、インドをIT大国へ成長させた大きな要因となっているのです。
インドのデジタル化も進んでいる
AppleやMicrosoftの本社があるシリコンバレーでは、インド人エンジニアも多く住んでいます。シリコンバレーは白人優遇の雰囲気がなく実力主義のため、インドや海外のエンジニアが多く働いているのが特徴です。
アメリカのIT企業などが積極的にインド人を採用しており、前述の通り1,000万円を超えるオファーを出すこともしばしば。そのためインド人技術者は海外に出ていくことが多かったのですが、最近では母国に帰ってデジタル化を進める流れがあります。
アメリカで経験を積んだエリートエンジニアが自国のIT産業をけん引することで、インドのデジタル化は日本を追い越すと予想され、注目が高まります。今回のOKCreditも、その1つと考えられるでしょう。
参照:The SC Startups 100「インドエリートの台頭。インドのデジタル化は日本を超える」
https://svs100.com/iss-3-2/
インドに進出する日系企業も増えている
半数近くは製造業
2017年時点で13億人の人口が集まるインドは、日系企業も市場を広げる目的で進出しはじめています。JETROの発表によると、2018年時点でインドに進出した日系企業は前年比で5.3%上昇。数にして72社の企業がインドへと進出しています。
Panasonicやスズキといった大手企業もインドに進出し、在インドの日系企業として成功。JETROの調べでは、インドに進出する日系企業は、製造業が49.7%と半数を占めています。次に輸送用機械器具(11.9%)、化学工業(5.6%)と続き、新しく食品業界も参入を始めました。
州で見るとインドのハリヤナ州に拠点を置く企業が多く、日系企業のおよそ3割を占めています。主要工業地域であるため進出しやすい環境であり、自動車メーカーのスズキも向上を構えています。
参照:JETRO「インドへの進出日系企業が着実に増加」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/12/c623b21a81ba3407.html
インドに進出するも苦戦する企業は多い
日本の10倍以上人口が集まるインドではビジネスも成功しやすいイメージがありますが、インド独自の規制や問題があり、日系企業は苦戦を強いられています。
まず問題となるのが人件費です。日系企業がインドに進出する場合、日本人を駐在員として派遣するのが一般的。インドは日本よりも個人所得税が高く、その税金は会社側が負担する傾向にあり、“実質赤字”となる企業が増えているのです。
また、インドには「Made in India」のスローガンがあり、原材料もインド現地で調達してほしいという国の考えがあります。そのため原材料に対する関税負担が重くなり、税金の影響でビジネスモデルの見直しを強いられるケースも無視できません。
高品質で高価格の日本製品よりは、品質が多少悪くとも廉価製品が売れる傾向も強く、日本の大きなアピールポイントである「品質の高さ」を武器にできない点も難航する原因です。
今後インドを視野に入れている店舗は、インドの市場や政府の考えを理解した上で販売戦略を練る必要があるでしょう。
参照:WEDGE Infinitu「インドに進出した日本企業が苦戦しているワケ」
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15474
無印がインドで成功した理由
無印良品を展開する良品計画は、2016年あたりからインドへ進出しています。すでにムンバイ・バンガロール・ニューデリー・ノイダとインド内で4店舗の出店を果たし、インド人に受け入れられています。
2017年度のデータですが、無印良品は日本よりもインドのほうが客単価が高いのが大きな特徴。日本が2,300円であるのに対し、インドでは5,000円以上になっています。文具・化粧品・生活用品などが売れ筋で、「シンプルなデザインが良い」「高いけれど品質が良い」と好評です。
良品計画は、インドの地元財閥であるリライアンス・インダストリーズ(RIL)と提携を深めることで、インドでの商売に成功しています。
現地調達を重んじるインドに合わせ、商品の現地調達も開始。RILが紹介した仕入先や工場と契約することで、品ぞろえを増やすこともできました。
参照:リテールテックJAPAN「無印、インドで元気印、財閥と旗艦店、現地で調達、客単価、日本の倍、初のスマホ決済へ。」
https://messe.nikkei.co.jp/rt/news/135903.html
無印良品のスマートフォン向けアプリ「MUJIパスポート」のインド向け配信も開始。無印良品ファンの拡大に向けて、デジタルマーケティング戦略も進めています。
参照:良品計画「無料スマートフォンアプリ「MUJI passport」インド版がスタート」
https://ryohin-keikaku.jp/news/2018_1102.html
国が変われば、店舗運営で採るべき戦略も全く変わります。しかしIT技術を使った戦略は、今やどの国でも必須となるでしょう。