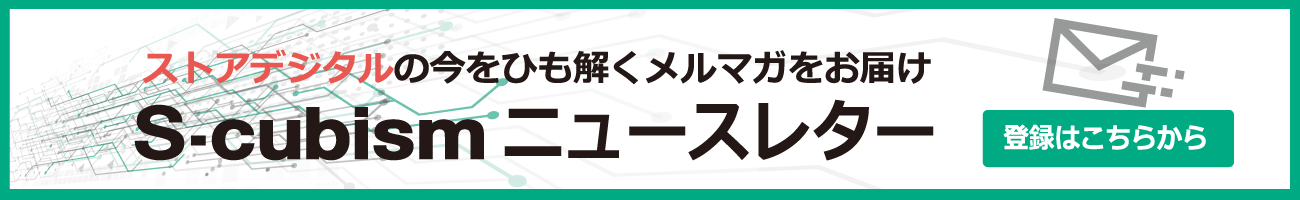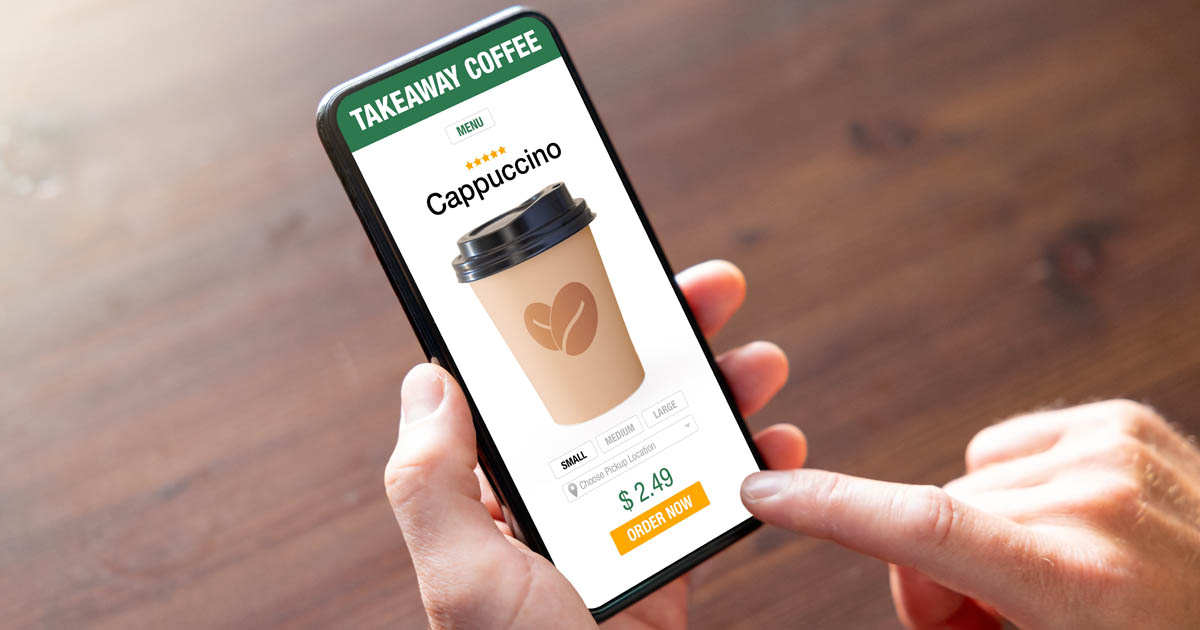ポップアップストアは店舗マーケティング施策の定番に。目標を定めることが成功の鍵となる

期間限定で出店するポップアップストアは、ブランド(商品)の認知、ECサイトへの顧客誘導、ショールーミングをはじめとした体験の提供など、さまざまな役割を担えるプロモーション方法のひとつです。
日本でその存在が知られるようになってから約10年、コロナ禍を経てその注目度はますます増しています。
適切に運用することで、低コスト、低リスクでの目標達成が可能になるポップアップストアは、細分化する顧客ニーズ、人手不足といった問題解決の糸口にもなり得る施策です。
本稿では、ポップアップストアがどのような場であるのかという基本をおさえるとともに、AIカメラやポップアップストア運営会社によるプロモーションなど、ストア最前線の模様を紹介します。
無料メルマガ登録はこちら:ストアデジタルの今をひも解くメルマガをお届けポップアップストア10年の変化
ポップアップストアは、Pop-Up(突然現れる、突然起こる)という名前の通り「突然登場して、期間限定で運営する店舗」のことです。期間はストアによってさまざまで、数日間のみ運営されることもあれば、数週間から一ヶ月にわたって運営されることもあります。
ポップアップストアは、長期的に固定の店舗として出店するよりも、かけたコストに対してリターンを読みやすいというメリットがあり、出店自体が広告的な役割を担うという利点もあります。
ポップアップストアの歴史
日本にポップアップストアという概念が普及し始めたのは、10年ほど前です。
欧米を中心としてまず広がり、2015年頃には日本にもこの概念が広がり始めました。
コロナ禍以降、緊急事態宣言で外出が制限されると小売店舗の閉店や大型商業施設のテナント退店が相次ぎましたが、同時にECが急速に普及したことにより、空きテナントをポップアップストアのスペースとして運用する動きが活発化しました。
ある企業の調査によると、ポップアップ出店の人気スペースは、首都圏、地方都市ともに百貨店やショッピングモールなど施設内の一角です。
こうした施設は、もともと人の流れがあり、SNSなどの告知プロモーションを見ていない人でも足を止めやすい、買い物のついでに立ち寄ってもらいやすいという立地と言えるでしょう。
従来のポップアップストアといえば比較的省スペースに出店するのが一般的でしたが、体験型イベントなどの流行によって広いスペースでの出店も増加してきています。これに伴い、百貨店やモール型店舗以外の場所にもポップアップストアを出店する動きが見られるようになってきました。
同じ調査によると、ポップアップ出店を経験した事業者のうち、出店に何の効果もなかったと回答したのはわずか1%というデータがあります。
出店者はブランドの認知向上、新規顧客の獲得、売上の獲得など何らかの効果を実感しているものと想定されます。
初期は商品販売やテストセールスの場
初期のポップアップストアは、テストセールスの場という意味合いが強く、やや限定的な活用をされていました。
これは、ポップアップストアでその地域の反応をチェックし、手応えが掴めれば固定店舗の出店を検討するというものです。ポップアップストアの売上が好調であれば、その場所や近い商圏に正式出店した場合も成功が見込まれます。
まだ実店舗を持っていない場合、ECサイトの期間限定実店舗として出店することにより、D2C(Direct toConsumer、卸業者を通さずにメーカーが直接商品を販売するビジネスモデル)へと転換することも可能です。
ECの利用が急速に拡大した2019年以降は、D2Cモデルへの転向が世界的に活発化しました。ポップアップストアが奏功した事例も多数あります。
マーケティング施策の定番として浸透
ポップアップストアは、新商品の発表、限定品の販売を主たる目的として出店するマーケティングイベント型店舗が一般的ですが、他にもシーズン限定、実験型、モール施設などに出店するショップ・イン・ショップ型、仮想空間に出店するバーチャル型など、多様なタイプがあります。
ポップアップストアは、達成したい目標に合わせてさまざまな出店スタイルを選択できるため、マーケティング施策の定番としてアパレル、飲食、サービスといった多くの業界に浸透していきました。
テナント側のメリットも
ポップアップストアを出店する企業のメリットは、人件費や賃貸料といったランニングコストを低く抑えられることですが、一方で、テナント側にもポップアップストア施策が施設全体の集客につながる、次々と新しいブランドが出店することで新しい価値を消費者に提供しやすくなるといったメリットがあります。
また、さまざまなポップアップストアが出店することでテナント同士の連携が生まれ、施設全体の活性化につながります。
以前には大型ショッピング施設とは、「交通の便がよく人を集客しやすい」という点が最大の価値とみなされてきました。
しかし、ECでいつでもどこでもあらゆる商品が簡単に購入できるようになった今、「地の利」のみでは求心力を維持することが難しくなりつつあります。
ポップアップストアという新風が吹くことで、商業施設に「交通の便」以外の新しい価値や連携するパートナーが生まれる可能性が高まるでしょう。

AIでデータも取りやすく。ポップアップストア最前線
短期間の出店で効率よく目標を達成し、次なる目標へとつなげるために、ポップアップストアの出店戦略は進化しています。
近年では、ポップアップストアの出店増加に伴い、イベントスペースの検索サービスや、スペースの予約を行うサービスが台頭、出店をプロデュースする運営会社も増えています。
さらに、AIカメラを駆使して人流や顧客の視線などをリアルタイムかつ詳細に分析することで、より精度の高いデータを取得できるようになっています。
2025年のポップアップストア最前線情報をまとめました。
運営会社が増加、相談しやすく
ブランドや商品の認知度を高めるためにポップアップストアを出店する場合、まず自社の強みを分析し、客観的に把握する必要があります。
その上で、トレンドや消費者の購買傾向をチェックし、ターゲット層にマッチするストアコンセプトを設計しなければなりません。
並行して、出店エリアや施設のリサーチ、ストアのレイアウトやデザインの設計、SNSなどによる告知プロモーションなどを進めていく必要があります。
移り変わるスピードが加速し続ける時流を読み、プロモーションを成功させるのは至難の業です。
しかし近年では、ポップアップストアを手掛ける専門の運営会社が増加傾向にあり、一から企画を練らなくてもノウハウを提供してもらうことが可能になっています。
目的に合ったスペースを探せるマッチングサービスやポップアップストア専用の予約プラットフォームもあり、外注できる部分が多くなっているのが特徴です。
インパクト重視のストアや、トレンドの波に乗りやすい仕掛けなどを取り入れることで、ポップアップストアは集客や売上UPといった目標を達成しやすくなるでしょう。
デジタルツールの発展によりデータの見える化が進む
フード業界のポップアップストアでは、AIカメラの活用がリアルタイムの消費者データ取得に一役買っています。
AIカメラは、撮影した映像データをAIで分析するもので、人が滞留しやすい場所や視線が集中する場所など、さまざまな行動をデータで取得することができます。
フード系のポップアップでは混雑で製造が追いつかなくなったり、反対に製造しすぎて廃棄が出てしまったりといった課題がつきものですが、AIカメラのデータをリアルタイムで用いることで、オペレーションの効率化がはかりやすくなります。
さらに、POSデータと組み合わせることにより、人流と売上の相関が明確になり出店後の戦略も立てやすくなります。
商業施設全体がポップアップストアに
従来のポップアップストアは、百貨店や駅ナカのイベントスペースやマンスリーレンタルのテナントに出店するのが一般的でした。
現在では撮影スタジオや展示会場など、小さなスペースから大きなスペースまで、さまざまな場所での出店も見られるようになり、1フロアが丸ごとポップアップストア貸出用のスペースになっている商業施設もあります。
こうした施設では、内装費用や賃料不要、什器のレンタル料金のみで出店できるメンバーシップ制度をとるなど、ポップアップ出店誘致のために施策を展開しているケースもあります。
従来のショッピング施設のテナント契約は年単位が基本でしたが、物価高や人口減少といった要因により、ショッピングのあり方は大きく変容しました。なるべく一人当たりのLTV(顧客生涯価値)を上げていくためには、常に新鮮な感動と驚きを演出し、訪れる人の満足度を高めなければなりません。
施設側は、さまざまなポップアップストアが頻繁に入れ替わることで、消費者に繰り返し来店してもらいやすくなる、人流が活発化するという期待をしています。
ポップアップストアで「何をするか」は明確にすべき
ポップアップストアは、それ自体が実験的な存在のため、壊滅的な失敗のリスクは少ないと言えるでしょう。
しかし、何を目的として出店するかをあらかじめ明確にしておかないと「リスク要因はなかったが、これといって成功と言える事象もない」という状況で閉店を迎えてしまう可能性もあります。
ポップアップストア自体の売上を上げることを目的とするか、あるいは体験型ポップアップからECサイトへの流入を主たる目的とするか、何をゴールに掲げるかはさまざまです。
目標が曖昧で定まらないという場合は、専門の運営会社やコンサルタントの力を借りるのも良いでしょう。
一般的なポップアップストアは、アパレルならばショールーム的な位置づけで出店することが多く、飲食ではバレンタインデーやホワイトデーといったイベントに合わせた出店をするのが一般的です。
とはいえ、ポップアップストアはこれら以外の実験的な取り組みが話題となって一つのトレンドを作り上げることもできます。
常識にとらわれることなく、目標を達成できる新しい形を模索していくことも重要かもしれません。