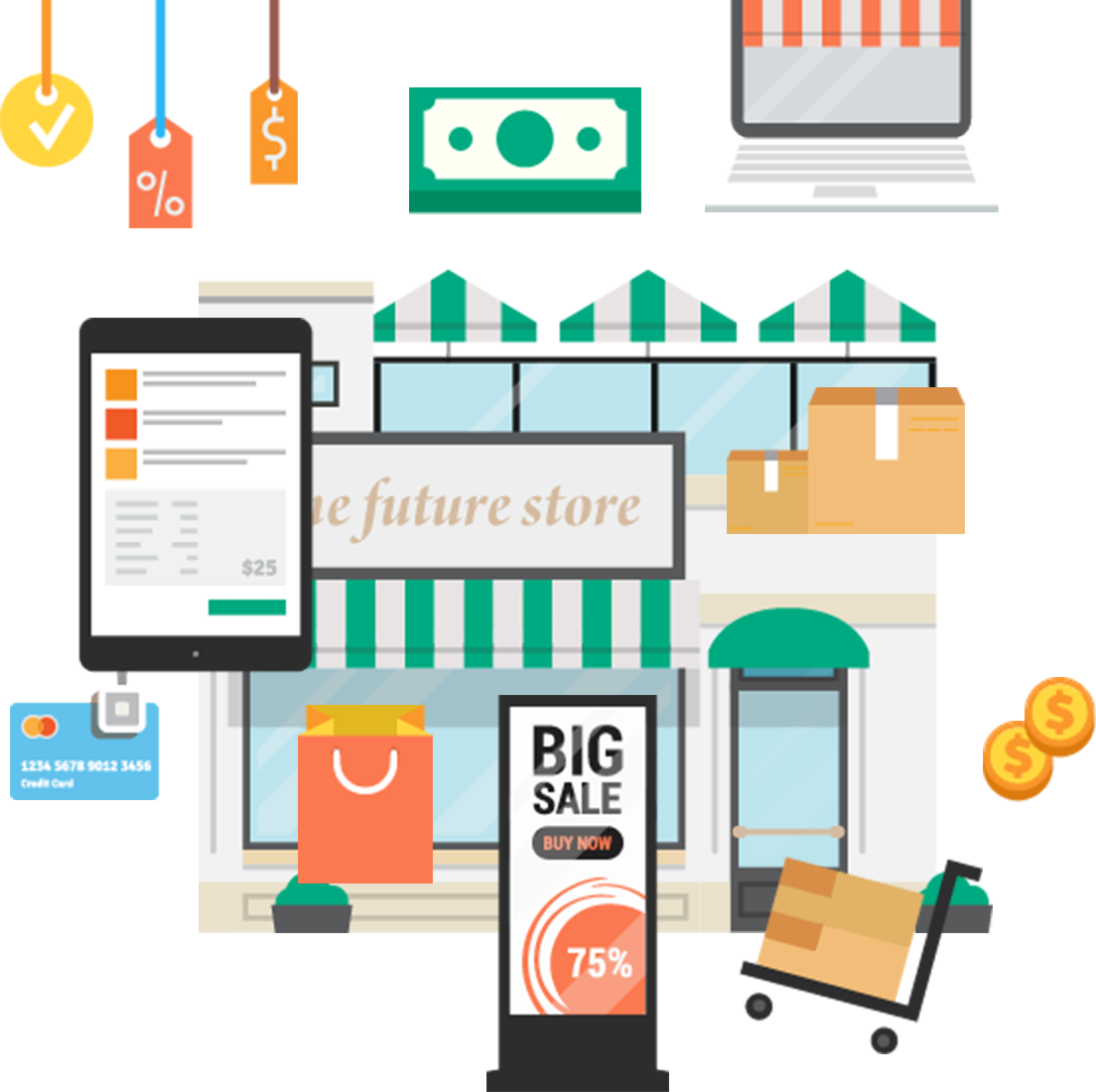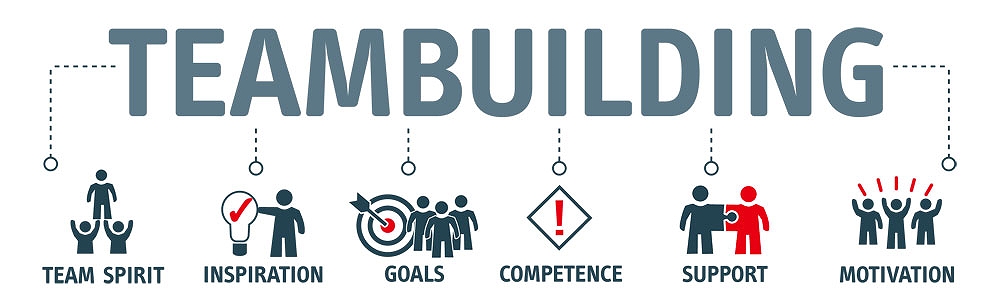店舗運営のAtoZ全31回
Lesson4 マーケティング編
16店舗ブランディングの進め方未学習
この講座は約8分で読めます
その効果の高さから、多くの店舗で採用されているマーケティング手法の1つに、「店舗ブランディング」と呼ばれる手法があります。
マーケティング編第3回目となる今回は、このブランディングについてその概要や作り方を、以下の項目にのっとって解説してまいります。
- 店舗ブランディングの進め方
- 商品・サービスのブランド力構築
- 「人」のブランド力構築
- 「店」のブランド力構築
- まとめ

店舗ブランディングの進め方
店舗ブランディングとは、簡単に言ってしまうと「店としてのブランド価値を作り出す」ことであり、
- 高い商品の質
- 個性(オリジナリティ)
- 付加価値
- ブレないコンセプト
などが、ブランドの構築には必要になってきます。
店舗ブランディングが成功すると、お客様がその店舗に掲げられた看板を見るだけで、即座に提供される商品やサービスの質、場合によってはその価格まで容易に想像できます。
そして、一度店舗のブランドイメージが固まると、以降大きなコストをかけなくても継続的な顧客の創生や、流出防止などに繋がっていくため、非常に有効なマーケット手法としてもてはやされています。
なお、すでにブランド化している、コンビニやファミレスなどといった「FCチェーン」への参加は、ロイヤリティーが発生するものの、それを最も簡単に実現できる店舗の形ではあります。
ですが今回の記事では、そういった母体となる運営企業が大きい既存のFC店ではなく、個人で運営する店舗におけるブランディングの進め方について、お話を進めていきます。

商品・サービスのブランド力構築
皆さんが、「ブランド」という言葉を聞いて真っ先に想像するのは、シャネルやルイヴィトン、イブサンローランなどといった世界的ハイブランドかも知れません。
また、例えばスポーツ用品であればナイキやアシックス、もっと身近な食品であればハウス食品や味の素なども、品質と安全性が信頼されているれっきとしたブランドとして、認知されています。
このように、まず初めに多くのお客様にとって「ブランド」として認識されてくるのは、その商品を製造・販売しているのがどの企業であるか、という点になります。
そして、名前も知らないようなメーカーのものより名前の知れたメーカーの商品を、多少価格が高くても購入するのが、お客様の心理です。

また、野菜や魚、肉などの生鮮食品の場合では「それがどこでいつ採れた(獲れた)のか」というのも、大きなブランド力になってきます。
ですので、上記のような商品を販売する小売店の場合では、お客様が「ブランド商品」として信頼を寄せている商品をラインナップすることで、おのずと店舗自体のブランディングに効果が出てくる可能性もあります。
ただこの場合でも、マーケティングによって今世間がどの商品にブランド価値を見出しているのかを把握し、日々商品を入れ替えたり、POPなどの販促ツールやセールストークで、しっかりアピールすることを忘れないようにしましょう。
問題は、商品自体を自らの店舗で製造・販売をしている店舗の方で、この場合のブランディングは、少々テクニックと工夫が必要になります。
例えば食料品なら、
- 無添加
- 無香料
- 無農薬
- 独自製法
などをアピールするのもいいですし、飲食店であるなら提供するメニューの中に、「ここでしか食べられないモノ」を入れるなど、商品に「オリジナリティー」や「付加価値」を持たせることが、店舗自体のブランディングへ繋がっていきます。

- 【ここがポイント!】
~時にはチャレンジスピリッツも必要~ - お客様は、確かにブランドが持つ「普遍的な商品価値」を求める傾向にありますが、それと同時に「独創性」や「プレミア感」などといった、ベネフィットも併せ持っています。
例えば、1杯2,000円の特製うどんに興味を抱く方も多く、通常メニューの中にそれを紛れ込ませることで売れなくても、
「あのうどん屋さんには変わったメニューがある。」
という口コミの拡散を生み、店舗の個性確立というブランディングの第1歩を踏み出せる可能性があります。また、小売店であってもスタンダードな商品の中に、少々目先を変えた高額で挑戦的な商品を紛れ込ませるのも手です。
例えば、通常価格のお米の隣に非常に高いブランド力を持つ、「魚沼産コシヒカリ」を陳列した場合はどうでしょう。
「そういえばあそこ魚沼産コシヒカリを置いていたよ!」という話題つくりとなるため、これまた主婦層での口コミ拡散という、ブランディング効果が出る可能性もあります。このように、いつも変わらない商品・サービスを提供してくれる、という安心感も大切ですが、店舗ブランディングを進めていくには、時にチャレンジスピリッツを発揮して、ユニークな商品導入などの工夫をすること検討してみましょう。

「人」のブランド力構築
商品やサービスに、個性や付加価値を持たせ店舗ブランディングしていくことは、「経費さえかければ」、案外すぐに実行することができます。
ただその経費が問題で、できうる限り経費を抑えて、店舗ブランディングをしていきたいのが心情です。
そんな時は店長や運営者自身、さらにスタッフのスキルアップによるブランディングを、併せてやっていくと良いでしょう。
例えばフランスレストランに在籍している「ソムリエ」がおすすめしてくれるワインは、それがどういったものであるかよく知らなくても、その言葉を「信頼」して選ぶことも多いはずです。
つまり、ソムリエという「肩書」がお客様にとって、「ブランド」として認識されているということです。
そして、自分のお店のスタッフに、このソムリエのように信頼感を持たれる「肩書」があれば、店舗の商品やサービスを変えなくても、店舗ブランディングは可能になってくるのです。

また世の中には、「○○マイスター」や「△△アドバイザー」など、商品やサービスのブランド力を上げる様々な資格制度がありますが、実在する肩書でなくとも、お客様からの信頼を得ることはできます。
この店に来れば、「置いてある商品・サービスにとても詳しいスタッフがいる」、というイメージをお客様に持ってさえもらえれば、それは立派な「肩書」となり店舗ブランディングの一環として、しっかり機能してくれます。

- 【ここがポイント!】
~肩書を作ってしまうのもアリ~ - 実在する数々の肩書を、しっかりと勉強して取得していくのが最も手っ取り早いですし、お客様からの信頼アップ効果は高くなってきますが、肩書が存在しない商品や取得が非常に難しい資格などもあります。
しかし、肩書といったものは店長や運営者が、独自に作ってしまってもいいもので、相応の商品知識や販売スキルを身に付けたスタッフに、リーダー・主任・SV(スーパーバイザー)などといた、店舗における肩書を付けてあげるだけでも、ブランディング効果は出てきます。またこの手法は、自分のスキルや販売成績を、しっかりと店長や運営者に評価してもらえたとスタッフが感じるため、そのモチベーションを維持する追加効果も望めます。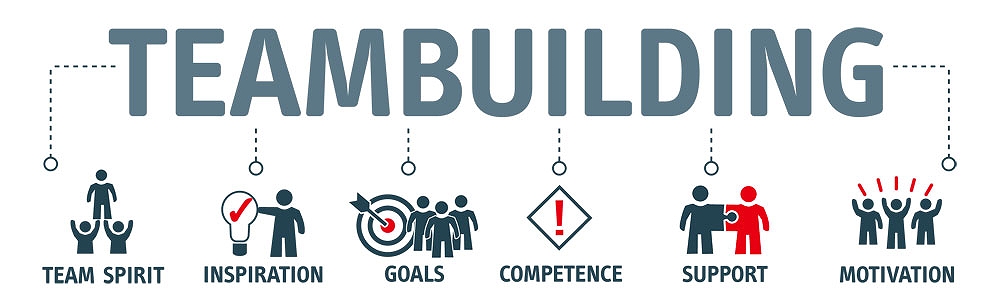
「店」のブランド力構築
「商品・サービス」と「人」のブランド構築がうまくいけば、もう店舗ブランディングの完成はすぐそこです。
あとは、構築してきたブランド力を発信できる「店作り」をするだけで、
- 話題の○○が買えるお店
- △△のエキスパートが在籍
などといった具合に、店舗の外装やのぼりなどの販促ツールによって、街行く顧客候補にしっかりとアピールするとよいでしょう。
また、SNSなどによる口コミの拡散も大切ですし、自店舗のHPを作成し自慢の商品とサービス、そして優秀なスタッフ達を、少々オーバーでもいいですから自慢するようにしましょう。
加えて、店舗としての立ち位置、つまり「コンセプトの維持」を意識しておくことも大切です。
せっかく商品やサービス、スタッフにブランドイメージを持ってもらえたのに、それらがコロコロ変わってしまっては、お客様の信頼感が下がってしまうこともあります。
ある程度ブランディングが進んだら、商品やサービスを固定したり、スタッフの待遇改善などを行って、「ゆるぎないコンセプト」の確立を併せて進めていきましょう。

- 【ここがポイント!】
~継続することが大切です~ - 店舗ブランディングは、よほどのヒット商品でも生み出さない限り、じわりじわりと進んで周辺のお客様に浸透していくものです。
商品やサービスの品質維持やスタッフの教育、そして発信力のあるお店作りは、流動する市場の情勢に合わせて、継続して実施していく必要があります。また、ブランドイメージが1度店舗に付けば、それが長期間にわたって持続することも、この店舗ブランディングという、マーケティング戦術の良いところです。ただし、永遠に続くという訳ではなく、時間の経過とともにブランド力は少しずつ落ちてしまいます。商品やサービスの改良やスタッフへの再教育などといった、「定期的なメンテナンス」を意識しておくとよいでしょう。

まとめ
ここまで触れてきた、すべてのブランディング作業がうまくいって、店舗としてのブランドイメージがしっかりと付けば、うわさを聞き付けた新規顧客も集まり、店の運営はどんどんと安定し売上も向上していきます。
店舗ブランディングは、若干時間と手間がかかりものの、「コスト」はそれほどかからない上、得られるメリットは非常に大きいので、地道に1つ1つ作業を進めて、店舗の利益拡大に向かっていきましょう。

ここがまとめポイント!
- 店舗ブランディングとは、店のブランドを構築することである。
- 商品自体が持つブランド力を、うまく活用するのも効果的で、時には挑戦的な商品・サービスの採用もアリ。
- 自らの店舗で商品を製造している場合は、「オリジナリティ」や、「付加価値」を持つ商品開発が必要である。
- スタッフに肩書を持たせることは店舗ブランディングに加え、スタッフ自身のモチベーション維持にもなる。
- 作り上げた商品・サービス・スタッフのブランド力は、店舗の至る所で宣伝をし、積極的にお客様にアピールする。
- 小テスト
- 次のうち、記事内容と一致するものを1つ選んで、クリックをしてください。
- 【正解】2:店舗ブランディングでは、商品やサービスに加えて、スタッフのブランド力を上げていくことも大切。