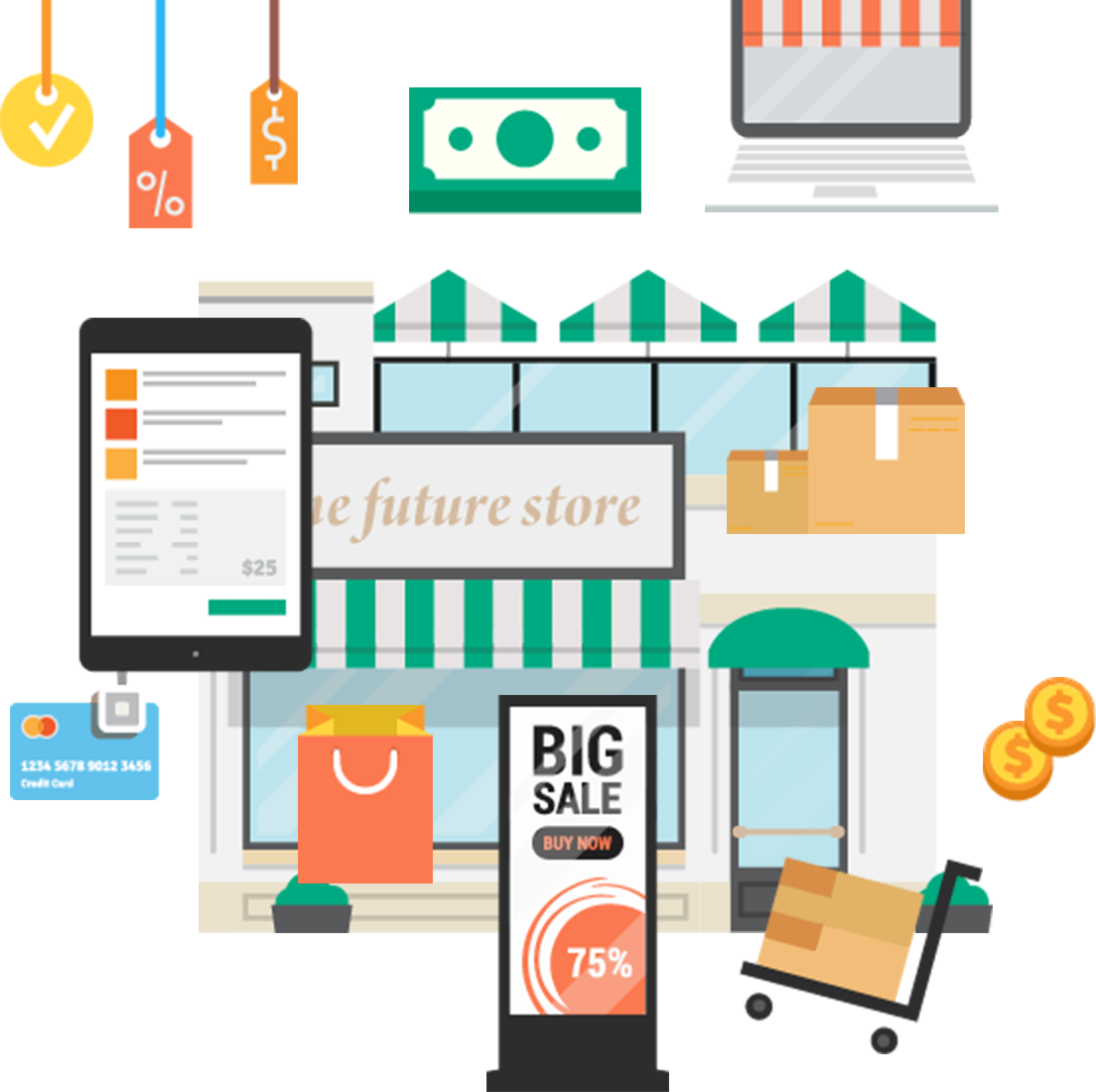店舗運営のAtoZ全31回
Lesson5 店舗のICT活用編
22配送管理システムの構築未学習
この講座は約8分で読めます
在庫管理システムの構築とその運用と併せ、在庫商品を補充するための発注量・配送スケジュールの決定をしなければなりません。
また、店舗にある商品をお客様へお届けする場合もあり、滞りなく行えるような配送管理システムを確立しておく必要があります。
今回は、配送管理システムとはどういうもので、ICTをどのようにその構築に活用していけば良いのか、以下の項目に沿って解説をしてまいります。
- ICTの活用による配送管理システムの構築
- 適切な在庫補充のための配送管理システム
- 確実な商品発送のための配送管理システム
- 外注による配送をする場合
- 自店舗で配送をする場合
- まとめ

ICTの活用による配送管理システムの構築
配送管理システムと一言で言っても、店舗の営業スタイルによって大きく2つのパターンの配送管理システムがあります。
一方は、原材料や商品そのものの補充をスムーズにするための、「店舗内配送管理システム」であり、商品やサービスを自店舗の中でのみ販売している場合は、こちらの構築と運用だけで十分なこともあります。
もう一方は、自店舗の商品を店外に向けて販売する場合に必要な、「店舗外配送管理システム」であり、これまでは主に製造業を中心としてその構築と運用が進んできました。
そこで、内部・外部それぞれの販売管理システム分けて、詳しくお話を進めてまいります。
1、適切な在庫補充のための配送管理システム
まずは、品切れや原材料不足による店舗営業の停滞を防ぐために、構築と運用を進めていく配送管理システムですが、こちらは前回解説をしたように「在庫管理」をICTの活用によって「システム化」に成功していれば、それを配送管理システムとして利用できます。

例えば、個人で経営している飲食店や小規模小売店の場合、パソコンなどICTの活用で在庫データの「見える化」をすることにより、在庫管理の正確性向上とスタッフとの情報共有がなされれば、適切な在庫補充が可能な「配送管理システム」として機能します。
また、スーパーやコンビニで広く活用されているPOSシステムは、在庫が少なくなった商品について、同時に管理している「販売時点情報」と照らし合わせ、適切な数量を自動発注する機能を併せ持っていることがほとんどです。
新商品の販売を始めるときや、季節の移り変わりなどに合わせ、調整を加える必要はありますが、基本的にはそのまま優秀な配送管理システムとして活用できます。
- 【ここがポイント!】
~インターネット化に伴って配送管理システムも多様化してきている~ -
自店舗内のみで、商品やサービスを販売している店舗の場合では、上記で述べた通り「在庫管理システム=配送管理システム」として、運用できることもあります。
とはいえ今では、Amazonや楽天市場などといった「ECサイト」に出店をし、離れた場所に住む不特定多数のお客様に、商品を販売・配送をしている小売店も多くなってきました。
また、スーパーやコンビニも遠方にお住まいで、日々の買い物が大変なお客様に配慮をした、「ネット販売・宅配サービス」を展開している店舗も急増しています。
- そしてこの場合では、以下で解説をする「外部」に対しての配送管理システムの構築・運用していくことも、その事業規模によっては検討しなければなりません。

2、確実な商品発送のための配送管理システム
一方、店舗で商品を製造して大量に外部の企業などに販売する店舗の場合は、受注した数量を素早く、確実に配送することができるシステムの構築が急務となっています。
また、前項の最後でお話ししたとおり、すでにネット販売に取り組んでいる、もしくはこれから参入しようと考えている小売店の場合も、外部に向けた配送管理システムの構築を検討していきましょう。
商品をお客様にお届けする方法には、「宅配業者への外注」と「自前の配送手段の整備」という2つのケースがあり、それぞれ構築していくシステムと活用するICTツールが変わってきます。

2-1外注による配送をする場合
大手宅配業者や、個人の運送業者に商品配送を依頼する場合は、外注コストはもちろんかかるものの、配送管理システムは自店舗内部のみで商品を販売するケース同様、非常に簡易なもので済みます。
なぜなら、そういった専門業者の場合、すでに配送管理システムが確立されているためで、それを活用する代金として「外注費用」がかかってくるのです。
このケースでは、注文された商品を規定の日時にキチンとお客様にお届けできるよう、パソコンなどで、
- 注文者の氏名と連絡先
などを管理すれば、店舗における配送管理システムとして十分に機能します。

ただし、ネットショッピングを利用したお客様の場合、「ちゃんと商品が届くだろうか…。」などといった不安を抱くことがあり、高額な商品になるほどその傾向が強くなってきます。
ですので、高額商品を値って経由で受注しそれを配送する場合は、メールによる「商品の配送状況お知らせサービス」など、お客様の不安を和らげるサービスを用意している、大手宅配業者をチョイスするのも良いでしょう。
また業者まかせではなく、パソコンで管理した個人情報を活用し、直接電話やメールによってコミュニケーションをとることにより、お客様の店舗に対する信頼度がアップすることもあります。

2-2自店舗で配送をする場合
一方、配送件数の増加や配送エリアが広範囲にわたった場合、外注では採算が合わなくなってくることもあるため、自店舗での配送を検討することもあります。
自前の配送体制を整備する場合は、ICTツールをフル活用した、本格的な配送管理システムの構築も視野に入れましょう。
具体的にやっていくことを整理すると、
- 配送車両とドライバーの確保
- 受注・配送状況の管理
- 配送スケジュールの決定と共有
- 配送状況の見える化
などといったものになり、1については物理的に必要数そろえることで対応できます。
また、2・3・4の段階では、パソコンによる受注・配送データの管理とともに、配送スケジュール表を作成し、携帯デバイスの活用によって、配送スタッフとのデータ共有を進めていきましょう。
活用する携帯デバイスは、配送件数や配送エリアの広さがまだそれほどではないケースでは、スマートフォンや一般的なタブレットで対応できます。
しかし、配送ボリュームやエリアが拡大してきた場合では、大手宅配業者が採用している、「PP※」の導入を検討していきましょう。
※PP:ポータブルポスのこと、「配達完了」や「不在時の持ち戻り」などといった情報の共有や、配送の進捗状況を「伝票」としてプリントアウトすることで、配送先で提示・投函することができる。

- 【ここがポイント!】
~配送管理専門部署の必要性~ -
ビジネスが拡大したり多店舗展開を進めた場合、配送体制も併せて充実させなければならないため、必要となる配送車両やドライバーの数がどんどんと増え、配送管理システムもそれに伴い複雑化してきます。
そのため、配送管理システムを運用する「専門部署」を設置したほうが、効率が良くなることもあります。
ただし、人件費・車両購入・管理費などに加え、配送管理システムの構築と継続運用にかかるコストも増大していくため、外注に頼ったほうが「費用対効果」が望める場合も出てきます。
ビジネスの拡大を視野に入れる場合は、複雑化する配送管理システムを自ら構築していった方がいいのか、外注に移行して簡素化したほうがいいのかをじっくりと吟味して、運営方針を決定していきましょう。

まとめ
商品を確実に、早く手元にお渡しできる体制が整えば、お客様に安心感と信頼感を与えることができ、リピーターの獲得や顧客流出の防止につながるため、店舗経営は長期にわたって安定していきます。
店舗の規模や業種によって、活用していくICTツールの種類や数は変わってきますが、自分の店舗にマッチしたものをチョイスして、有効活用をしていきましょう。

ここがまとめポイント!
- 配送管理システムには、原材料や商品の補充を円滑にする「内部向け」と、お客様へ確実かつ迅速に商品をお届けするための、「外部向け」がある。
- 中小の小売店や飲食店の場合は、在庫管理システムを運用することで、比較的容易に内部配送管理システムとしても利用することができる。
- Cサイトなどを利用して、商品を不特定多数に販売する店舗では、外部配送管理システムの構築も必要となる。
- 外注配送業者の利用なら、それほど複雑な配送管理システムを構築しなくても、パソコンなどの活用で十分に対応することができる。
- 自店舗で配送を行う場合は、配送車両や担当スタッフの確保とともに、携帯デバイスなどのICTツールを活用し、配送データの管理・共有を進めていかなくてはならない。
- 複雑な配送管理システムの構築と運用には、大きなコストがかかるため、その導入に際しては「費用対効果」について熟考する。
- 小テスト
- 次のうち、記事内容と一致するものを1つ選んで、クリックをしてください。
-
- 【正解】2:ビジネス規模の拡大に合わせて、配送管理システムの構築と、運用にかかるコストは大きくなってくる。