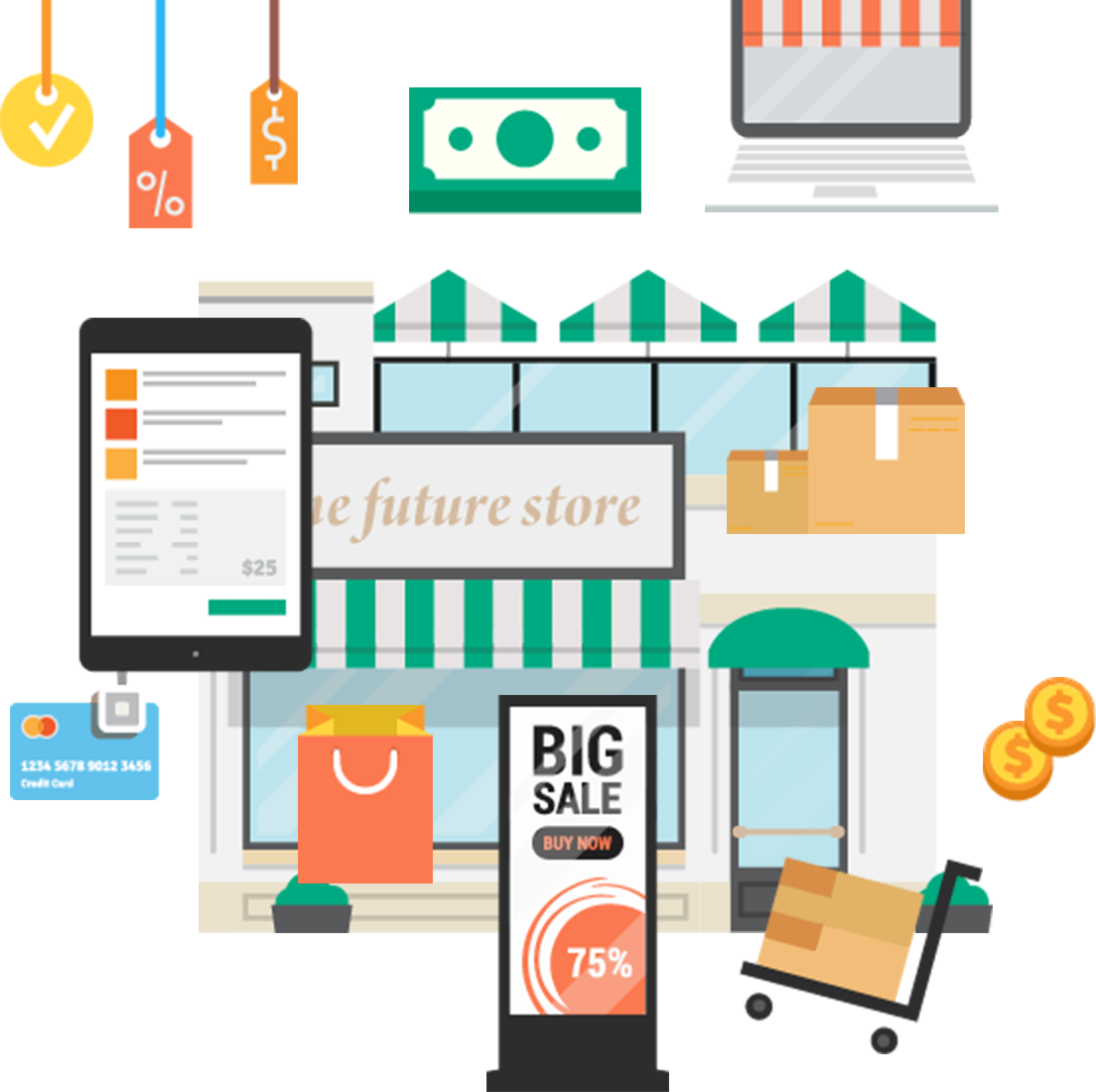店舗運営のAtoZ全31回
Lesson2 実店舗編
4店舗における効果的な商品配置とは未学習
この講座は約7分で読めます
限られた店舗スペースにおいて、いかに効率よくお客様の目に留まる商品配置ができているかどうかは、店の売り上げと利益を左右しかねない重要なポイントです。そこで、実店舗編第2回目となる今回は、販売実績の分析による店舗内での商品配置の決め方や、アピール力を高めるテクニックについて、詳しく以下の項目に沿って解説させていただきます。
- 商品配置はどう決めるべきなのか
- 販売実績の良い商品の配置
- 店舗の業態に合わせた商品配置
- 抱き合わせ購入を狙った商品配置
- 訳あり商品の配置
- 商品を目立たせるためのテクニック
- まとめ

商品配置はどう決めるべきなのか~販売実績の分析と業態を考慮すべき~
小売店において、売れない商品を何も考えずに配置し続けていても、一向に販売実績はアップしません。
売れないのなら撤退するというのも手ですが、販売実績を分析してうまく配置を変えることで、一転して売れ筋商品に生まれ変わることだってあるのです。

1、販売実績の良い商品の配置
まず、販売実績の良い商品の配置ですが、それがなぜよく売れるのかについて、つぶさに分析をしなければなりません。
商品自体が時節に乗っており、お客様の方から探しに来るような人気商品の場合、在庫をアピールすることにより、集客力の向上が見込めます。
ですので、目立つ位置への配置換えやPOPの追加、さらには在庫があることを伝える張り紙を店外にして、その存在をアピールしましょう。
一方、流行モノや人気商品ではないにもかかわらず、店内で売れ行きが伸びている商品は、配置の良さによって、販売実績が上がっている可能性があるため、あえて配置変更をしない方がいいこともあります。

- 【ここがポイント!】 ~販売実績の分析を間違えると大変~
- なぜ売れているのかを分析せず、安易に配置転換をしてしまうと、せっかく伸びていた販売実績が、返って下がってしまう可能性があります。
ですので店長や運営者は、A/Bテスト(※)を応用し商品配置を複数試して、最も売り上げが伸びる配置を探してみるのもいいでしょう。※A/Bテストとは、webにおける宣伝効果を試すマーケティング手法で、2つもしくはそれ以上のwebデザインにおいて、どれが最も効果的かを調べるテストのこと。
2、店舗の業態に合わせた商品配置
一言で小売店といっても、販売している商品はそれぞれ違い、取り扱う商品に合わせた商品配置をしなければ、決して売り上げはアップしてきません。
例えばコンビニチェーンやスーパーでは、どこも店内での移動と買い物がスムーズにできるよう、しっかりと導線が確保されているうえ、すぐに商品の確認をしやすい配置がなされています。

これは、「購入するものが決まってるから、時間をかけずに買い物できた方が良い」と考える来店客のニーズに合わせた、
「コンビニ流商品配置」
と呼ばれるスタイルで、現在多くの小売店舗で採用されています。
具体的には、
- パン屋
- 弁当屋
- ドラックストア
などといった主に「日用品」を取り扱う小売店では、コンビニ流の商品配置スタイルを取るといいでしょう。
ですが、ブティックやジュエリー店、骨とう品店などがその代表格ですが、生活必需品とは言えない商品を販売する店舗の場合、「いいものが見つかれば買おう!」というのが、来店客のスタンスです。
こういった店舗の場合、先に述べた「コンビニ流商品配置」をしてしまうと、必然的に来店客の滞在時間が減り、「衝動買い」を引き出す機会が減ってしまいます。
ですので、陳列棚を縦横に組んで店内の移動をしにくくしたり、商品配置の高さをずらしたりして、あえて商品を見て回るのに時間がかかってしまう、意図的なレイアウトをするのも手です。

- 【ここがポイント!】 ~ぐちゃぐちゃで良いという訳ではありませんが…~
- 雑貨屋さんや、リサイクルショップなどは特にそうですが、来店したお客様のなかには掘り出し物を見つけたいという、「宝探し」的な楽しみ方をする方もいます。
全く整頓せず、むちゃくちゃに商品配置をしても大丈夫という訳ではありませんが、時にはセール品をワゴンに満載したり、ドン・キホーテのような所狭しと陳列する方法も参考にしてみましょう。

3、抱き合わせ購入を狙った商品配置
店舗にある商品には、
- 食パンとジャム
- おでんの具材と和からし
- エプロンと調理用品
- ソファーとクッション
のように、それぞれ関連性の強いものがあります。
これらを、うまく組み合わせて配置することにより、抱き合わせによる一斉購入を狙うこともできます。
また、購入後に食べたり着たりしている姿を想像させ、購入意欲をアップする効果も併せて見込めることから、この配置法を採用するところもかなり増えてきています。
- 【ここがポイント!】 ~時には変わった組み合わせをしてみるのもアリ~
- 関係性がわかりやすい商品を組み合わせ、配置するのがセオリーですが、「なんでここに?」と思わせる突拍子もない商品配置をしてみるのも、来店客の滞在時間を伸ばすという効果を狙えます。
例えば、購入後の用途に合わせ、「サンマの隣におろし金」
「エビの隣にパン粉」を配置するなどといった具合に、一手先行くユニークな商品配置をスタッフ全員でアイデアを出し合いながら、考案するのもいいでしょう。

4、訳あり商品の配置
こちらも、今や多くの小売店が行っていることですが、
- 消費・賞味期限の近い食品類
- 展示品や型落ち商品
- キズや色あせが目立つ商品
などといった、訳あり商品を並べている店舗もたくさんあります。

訳あり商品は、そのお得感から差し迫って必要ではない商品でも、来店客がついつい購入してしまうことも多いため、「レジ横」のように思わず手に取ってしまいそうな場所に、配置するといいでしょう。
- 【ここがポイント!】 ~店に入ってすぐ見える場所はNG~
- 廃棄しなければならない商品を、大幅に値下げしてでも販売し、何とか損益を最小限に踏みとどめたいのが、店長・運営者の心情です。
また、展示品として手あかがついていたり、目立たないとはいえキズなどが入った商品といっても、売り方によっては了承のうえで、お客様が購入してくださることもあります。
ただし、売り抜きたい気持ちが逸って目立つ場所に配置してしまうと、「売れ残りが多い店」という悪いイメージが定着しかねません。
ですので、訳あり商品を配置する場所はさりげなく、あまり主張しすぎない場所をうまく選ぶ必要もあります。

商品を目立たせるためのテクニック
店舗運営者は、その商品の原価に伴う純利益を計算に入れ、適切な商品配置を思案する必要があります。
そして、利益率の高い商品こそ来店客に最もアピールしたいところですから、店内で最も目立つ位置にある、「メイン陳列棚」への配置が基本になります。
また、メイン陳列棚の中でも最上段もしくは、来店客の目線にあった棚中央付近に置くと目に留まりやすく、売れ行きが伸びるといわれています。
さらに、POPなどを追加して商品を目立たせる工夫をすべきですが、人間の目は上から下、左から右へ動き商品を見るメカニズムのなっているため、POPは売りたい商品の「左上付近」に付けるようにしましょう。
- 【ここがポイント!】 ~販促・アピール素材つけすぎに注意~
- 商品配置に合わせて、それをアピールするPOPは確かに効果的ですが、多すぎると「この店は何押しなのか」がうまく主張できず、ぼやけてしまいます。
ですので、1つの陳列台につけるPOPは、多くても2つ程度に留めていた方がいいでしょう。また、同じ商品でも定期的にPOPの書体や色などを変えると、新商品な訳でもないのに改めて認知度がアップし、売れ行きが伸びることもあります。

まとめ
店長や運営者は、商品の売れ行き状況と自店舗の業態をしっかり分析し、それに合った商品配置に日々頭をひねる必要があります。
具体的な商品配置案を練るのは、皆さんの「知恵とアイデア」にかかってきますが、当記事がそのヒントとなれば幸いです。

ここがまとめポイント!
- 販売実績のより商品は、売れている要因に合わせた配置が大切。
- 取り扱っている商品によって、店内レイアウトを思案する。
- 実際に使ったり、食べたりしている姿を、来店客にイメージさせる工夫を凝らす。
- 訳あり商品の配置は、あくまでもさりげなく行うべき。
- 原価が安い商品をうまくアピールして、純利益のアップを狙う。
- 小テスト
- 以下のうち、今回の記事内容と一致するものを1つ選んで、クリックしてください。
- 【正解】2:取り扱う商品によっては、わざと導線を崩す店舗レイアウトをするのもアリ。